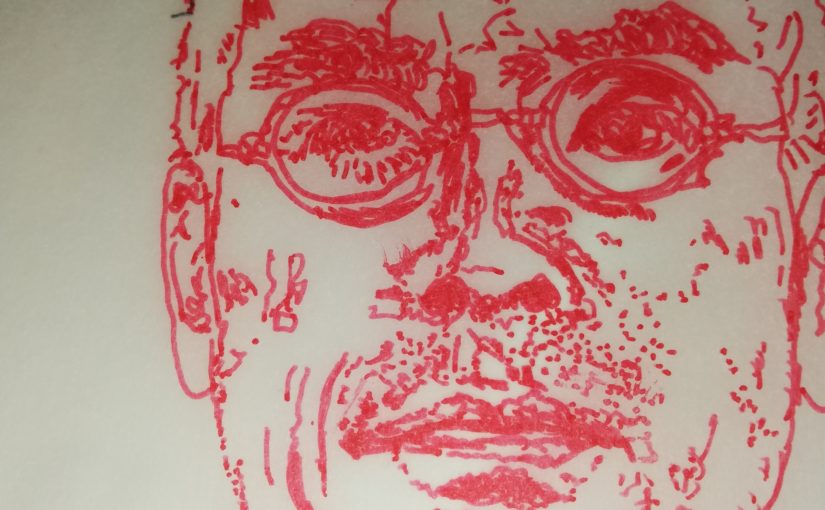こんにちは。花祭窯おかみ/アートエデュケーターふじゆりです。
読書『美学への招待 増補版』(中央公論新社)佐々木健一著
移動のお伴用にゲットした新書版。持ち歩くバッグが重くならないように(本が入ってなくてもまあまあ重いのですが)、タイトル指名買いでない場合は、できるだけ文庫サイズか新書サイズの本を物色するよう心がけています。
自分のやってきていること、考え続けていることがどうやら「美学」の範疇なのだと(かなり遅ればせながら)気づいたのは、昨年末に読んだ本のおかげでした。
せっかくなので少し掘り下げてみようと、「美学」キーワードで見つけたのが本書『美学への招待』です。「増補版」とある通り、2004年に初版発刊されたものを、2019年に時代に合わせて大幅にアップデートしたというもので、わたしが手に取ったのは、2024年10月25日付の増補版6版。初版から20年以上が経っているわけですが、まったく古臭さを感じないのは、増補=アップデートによる成果だけではなく、そもそもが根本的・普遍的なことについて書かれている本だからなのだと思いました。
以下、備忘。
- 人間の創造性が発揮される領域として、科学と並んで藝術が考えられていた、という事実
- 魅力とは、言葉にならないもの、感ずるよりほかにないもの
- 藝術の領域が美にあり、その美は感性的に認識される(ドイツの哲学者 A・G・バウムガルテン)
- 人格形成への美の影響
- 美は物質性と精神性の融合からなる
- 「美は体験のなかでしか存在しない」という考え方
- 感覚とは身体の持ち分であり、判断力というような知性の働きとは正反対の事柄
- 過去の経験の記憶や考え方のパターン、概念的な知識など、多様な要素が現実の鑑賞体験に関与し、それを重層的な和音のようなあり方のものにしている
- 哲学的な瞑想を行う場所(museumの由来となるラテン語mouseion)
- 美術とアートとartの違い
- マスプロダクションとしての複製と、オリジナルをコピーした複製(の違い)
- 生のなかの藝術
- 空間を人間化する(イサム・ノグチ)
- 「永遠」型の藝術
- 永遠派と現代派
- 藝術の価値をどこに見出すかという問題
- 藝術における伎倆の重要性の後退
- 「幸福の約束」(ネマハス)
- 「人生に不可欠」(ダントー)
- 「藝術」ももとは生活世界の一部だった
- 見てただちに捉えられる「よさ」とは、「美しさ」を措いてほかにありません。
『美学への招待 増補版』(中央公論新社)佐々木健一著より
本書はわたしにとって入門書であり教科書的な一冊となりました。巻末には、ここから先に進みたい場合に参考になる文献一覧と簡潔な紹介文が記してあり、とても親切。少しづつ読んでいきたいと思います。